統合レポート2025 対談:個を活かし、イノベーションで感性に響く価値を創出
2025年6月27日 公開
本ページはAIを用いて翻訳しています。
1995年に来日して以来、日本企業のサステナビリティ経営を支援し、次世代リーダー育成に幅広い知見をお持ちのピーター・D・ピーダーセン氏と、企業価値を向上させる組織運営について語り合いました。
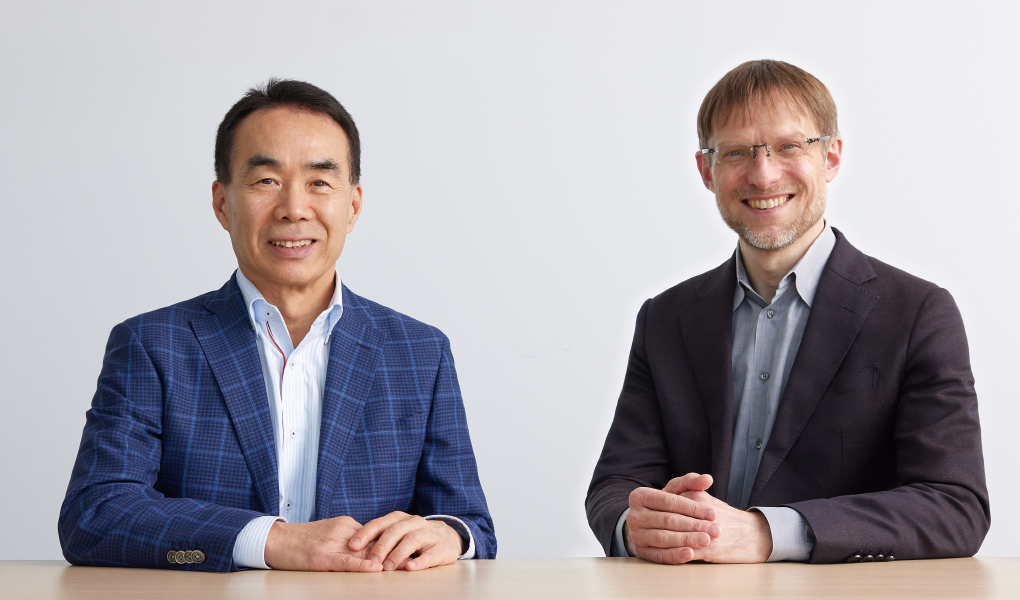
デンマーク出身の実業家。日本の高校への留学をきっかけに、日本の豊かな自然、歴史、文化、価値観に大きな可能性を感じ、1995年に再来日し、企業などのサステナビリティ経営支援に携わる。現在は、グローバルで次世代リーダーを育成するNPO法人ネリス代表理事などを務める傍ら、複数の日本企業の社外取締役も務める。
社名変更を旗印に、変革に挑む
髙島 社長に就任した2020年当時、コロナ禍もあり、当社の株価や業績は決して良い状況ではありませんでした。このままでは未来はない、変わらなければいけないという危機感から、変革の旗印として社名を変えました。
ピーダーセン artienceというのは、アート&サイエンスから付けられた社名だと伺いました。
髙島 はい。これまではサイエンスを標榜してきた我々でしたが、今後テクノロジーやAIが中心になる世の中では、あえてもっと「人」にフォーカスすることが大切だと思ったのです。サイエンスに加えて、心に寄り添う、感動を共有する、といった感性に響く価値(感性価値)、すなわち「アート」を提供していく企業になるという意味を込めた社名です。また、アートには「多様な解を受容する」リベラルアーツの思想も含まれており、良い命名になったと思っています。
ピーダーセン 面白いですね。普通は名前が理念を語ることはないけれども、artienceは社名そのものが理念を語っています。素晴らしいことです。
髙島 「感性に響く価値を創りだし、心豊かな未来に挑む」が当社の存在意義です。世の中の役に立ち、同時に心に寄り添うこと。この二つを追求しています。社内の座談会などで「感性価値とは」というテーマで議論してきたなかで、私自身、考え方が変化してきました。以前は「アイデンティティの普遍化」だと思っていたんですが、今は「人の幸せを願うこと」が感性価値だと思っています。現場の社員と対話するうちに「自分たちが作ったものが世に出て使われているのが喜びであり、それが感性価値だ」というような話が出てきました。視点が外にあるんですよね。利他を考えている。そういうことを社員との対話から学びました。
ピーダーセン 1997年に行われたアメリカの世界未来学会で、これからは「エクスペリエンスエコノミー」の時代だと言っていました。体感、まさに感性ですね。よい経験を提供する会社が勝っていくだろうということです。そういう意味でartienceの感性価値は素晴らしいですね。
個を大切にする人間尊重の経営
ピーダーセン 事業の海外比率が高くなっているそうですが、海外では「東洋インキ」よりもartienceのほうが通りが良いでしょうね。社員の受け止めはどうですか?
髙島 インキということにこだわる社員もいました。海外、特にアジアではまだまだインキが事業の中心ですから。一方、とてもポジティブに捉えている人も多いですね。この2年間、拠点を巡って座談会形式で若手や中堅と対話をしていますが、驚いたのはインドの社員たちが非常にポジティブに捉えていたことです。インド拠点の社名は「東洋インキインディア」ですが、自分たちもartienceに変えたいと言ってきており、理念も含めて賛同してくれています。
ピーダーセン アート&サイエンスを考えることが、コミュニケーションのインターフェイスになりそうですね。
髙島 2025年の1月から動画広告を配信しているのですが、そのなかで「私たちはものづくりの会社ではありません」「感動をつくります」「喜びをつくります」というメッセージを伝えています。そうしたら、工場の社員から違和感がありますと、私に直接メールが来ました。
ピーダーセン そういうことを社長に直接言ってこられる社風は素晴らしいですね。

髙島 はい、うれしいことでした。この社名はむしろものづくりを強調している、進化を見据えた社名である、ということを直接伝えています。対話する機会を増やしたおかげで、少しずつ変わってきたと実感しています。
ピーダーセン 日本の大手企業は組織文化で、とがった個を削ってしまう傾向がありますが、これからの時代、とがった個を引き出しながら目標に向かっていくことが重要です。自ら目標に進んでいくような人材が活躍できる組織が勝ち残るだろうと思います。
髙島 当社の経営哲学は「人間尊重の経営」です。個があって全体がある。組織のために個人が犠牲になることは絶対にあってはなりません。今、企業変革に取り組んでいますが、この哲学だけは決して変えないとしています。
ピーダーセン 一人ひとりの可能性を開花させ、人生を無駄にさせないことが企業にとって大切なことです。人的資本経営はともすれば形骸化しがち。個人の能力を最大化し挑戦を続けられるように、資本としての「人」を活かすことが一番重要だと思います。
個人が解放される組織づくりに挑戦
ピーダーセン 日本にはリーダーシップを持つ人が少ないと感じます。未踏の地に踏み込むような勇気を持つ人をバックアップする組織が理想ですね。7割は失敗するかもしれませんが、大きな挑戦をやっていかないと日本の産業界に未来はないと危惧しています。
髙島 当社グループの中核事業会社の一つ、東洋インキ株式会社は、もともと上意下達の企業風土が強かったのですが、ここが今、一番変わってきています。現場からどんどん提案が出てきているのです。その一つが「CXセンター」という新システム。人員を3分の1に減らしつつも、DXを利用して、テクニカルサービスや受注を行う仕組みで、彼らは顧客満足度を上げると断言して取り組んでいます。
ピーダーセン いいですね。個人が解放されることは、上意下達の組織ではできなかったことです。成果が出るのに5年、10年とかかりますが、会社は劇的に変容すると思いますので、挑戦し続けていただきたいです。
髙島 別の事例では、挑戦したい人を応援する仕組みとして、2021年よりビジネスアイディアコンテスト(現“IPPO”)を開催しています。4回目になりますが、どんどん進化しています。先程の東洋インキからの応募が一番多いのですが、印刷市場のシュリンクで苦しんだ4~5年を経験して、本当にハングリーになっている。業績も良くなって、投資家からもサプライズだと言われています。
ピーダーセン ビジネスコンテストを成果に結びつけるのは大変なので、素晴らしいことですね。イントラプレナー、社内に起業家がいるカタチは、日本企業に向いていると思います。ある程度リソースがあるなかで自由度を最大限にしていく。いろんな働き方や挑戦を包容できる組織になることが重要なんですよね。
髙島 一般的には、ビジネスコンテストは何年かすると応募数が減っていくそうですが、当社では逆に増え続けています。なかには十分可能性があると感じさせる案もあります。成功事例を増やしたいので、もっと応援する仕組みをつくろうと思っています。ある企画に対して、マーケティングやセールスの人がいないというので社内で募集したら、すぐに何人かが手を挙げてくれました。そういった一人の夢を皆で応援する仕組みができるかなと思っています。
ピーダーセン トップが方向性を示し、ミドルマネジメントが支え、最前線の部下が活躍できるという仕組みですね。
創造的ガバナンスを目指す
ピーダーセン 日本の企業は、監査やリスク管理、コンプライアンスは得意ですが、そちらにばかり気を取られるとイノベーションができなくなるのではと心配です。自由な機会探索が高い倫理性に支えられ、バックアップするためにガバナンスがある。誠実という文化をリーダー一人ひとりが現場で担保できるかどうかが問われるのです。
髙島 企業の倫理やガバナンスの違いは、生成AIの活用姿勢に顕著に表れているように思えます。当社は2024年から全社横串の「生成AI活用推進タスクフォース」を発足し、マテリアリティでも課題化しており、ルールを模索しつつも積極的に挑戦しようとしています。ところが、体制不備とか情報漏洩とかのリスクを最小化するために、AI活用を制限したり禁止したりしている会社もあると聞きます。
ピーダーセン ルールはバックアップするものであり、抑えつけるものではない。この転換が進めばいいですね。
髙島 ガバナンス改革として取締役会の改革から始めましたが、それによって会社は変わると思いますか。
ピーダーセン 変わります。まずは人選が重要ですね。私は複数社で社外取締役をしていますが、戦略議論をする会社もありますし、泊まりがけで合宿をする会社もあります。ある会社では、私はサステナビリティ委員会の委員長もしています。専門性と経験を持った社外取締役がそろうと、とても面白い議論ができます。創造的ガバナンスです。
髙島 会社が重視する分野のプロフェッショナルに社外取締役を務めていただくことは非常に良いですね。当社の社外取締役の方々にお話を伺うと、皆さんもっと関わりたい、もっと自分の役割を果たしたいと仰ってくださいます。
ピーダーセン そうなんです。時間の許す範囲でもっと踏み込んでいきたいと思うのが社外取締役なんです。
サステナビリティ課題に貢献し、企業価値を高める

ピーダーセン 日本は技術力や資金力だけでなく、非欧米的な自然観、近江商人の「三方よし」の考え方もある。私は、日本こそはサステナビリティ課題解決に欧米流とは違う道を示せるのではないかと思い、1995年に来日しました。でも今の日本企業はネオリベラリズムやグローバル金融資本主義、株主資本主義に流されてしまって、本来のポテンシャルを活かしきれていないのではと思います。御社の「感性価値」は、そこに立ち向かえるのではないかと。
髙島 私が社長として経営の軸としているのが渋沢栄一の『論語と算盤』なんですが、社会貢献と利益追求はトレードオフではなく両立だということ。株主の経済的利益だけじゃなくて、貢献との両立があって、真の株主資本主義と言えると思うのです。
ピーダーセン そうです。だからこそ上場企業はとても難しい判断を迫られるのです。
髙島 今、世界のあちこちで反ESG的風潮が起こっていますが、我々はメーカーとして温暖化抑止を責務としつつも、そこにビジネスチャンスもあるとしています。両方を追求するのが我々のサステナビリティビジョンasv2050/2030であり、これを翻すつもりはありません。
ピーダーセン それは良いですね。ESG活動がビジネスに結びつかなければマーケットで評価されない時代です。ビジネスに結びつくとは、ある意味究極の評価ですから。株主をいちステークホルダーとして大切にしながらも、振り回されるのは経営として違うと思います。
多様性のある組織が、多様な感性価値を生む
髙島 グローバル事業が進んで、売上高は5割以上、営業利益は6割以上を海外で挙げるようになっている今、人事部が取り組んでいるのが「グローバルな人材の流動性」を高める仕掛けです。社員も6割以上が海外ナショナルスタッフなので、タレントを世界に求めることで、イノベーションや企業価値も高まってくるだろうと思います。また、当社の取締役会もグループ経営会議も日本人ばかりなので、そこは大きな課題だと思っています。
ピーダーセン 本社のグローバル化は、多くの日本企業にとって大きな課題ですからね。グローバル人事の中枢をあえて海外に置いた企業もあります。本社にも外国人社員が増えたなと感じさせるくらい一定数採用したそうです。
髙島 海外拠点に関しては、年2回「グローバルマネジメントフォーラム」という会議を日本で開催していて、海外各社のトップマネジメントが日本に集まります。海外役員には女性もいますが、ただ多くはないんです。
ピーダーセン グローバルマネジメントフォーラム、とても良い取り組みですね。ぜひ続けるべきです。女性役員数もそうですが、女性社員の採用についても、先程の外国人採用と同様、あえて多くの人数をまとめて採ることが肝要です。そういった象徴的で思い切った取り組みをしないと、変化のペースは加速されません。
髙島 当社はまだまだ女性の比率が少ないので、戦略的に目標設定して取り組んでいるところです。
ピーダーセン 技術系やメーカー系は歴史的にどうしても女性が少ない傾向がありますが、どんなビジネスであってもユーザー視点で共感し考えるというのは、男性よりも女性のほうが得意であるケースが多いと感じます。そういう視点をもっともっと取り込むことは、artienceが感性価値の創出力を高めていくことにつながるでしょう。
髙島 artienceになってから、採用の応募数でも女性が増えているんです。アート&サイエンスの感覚が彼女たちに響いていれば良いなと思います。
ピーダーセン 響いているのでしょう。会社全体の変革を象徴するシンボリックな社名という感じで、今後に期待したいと思わせてくれます。
髙島 いろいろとご評価いただき、また重要な気付きもたくさんいただきました。本日はありがとうございました。
