統合レポート2025 artienceグループの強み:オープンイノベーション
2025年6月27日 公開
本ページはAIを用いて翻訳しています。
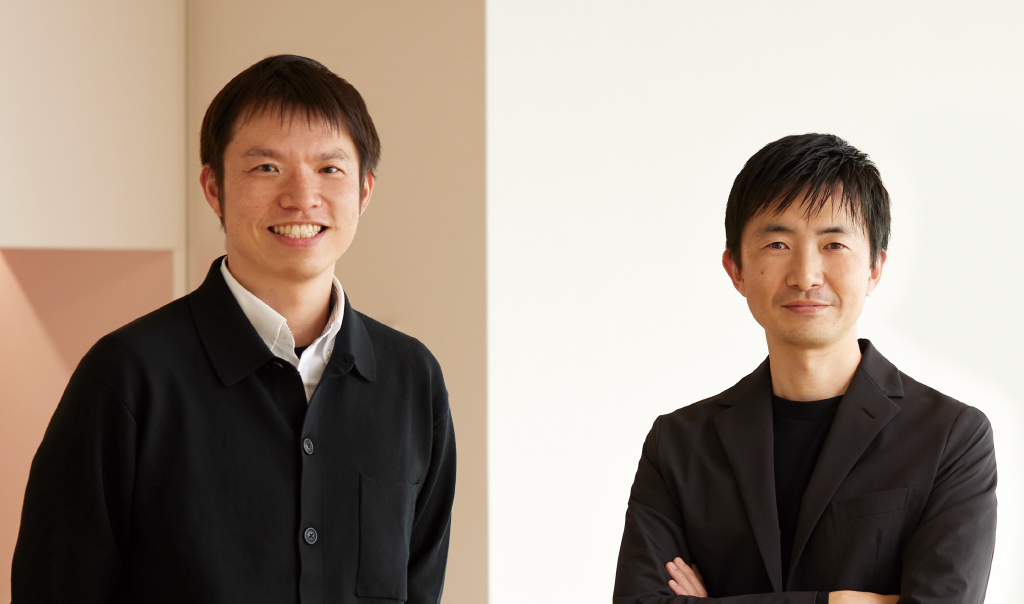
世界中から人と情報が集まる場を創り、協業と新事業創出を推進
インキュベーションセンター
次世代を支える新規事業の創出は、artienceにとって重要な経営課題の一つです。
インキュベーションセンターでは、従来の枠にとらわれないアプローチで「挑戦する企業風土」を醸成し、新たなビジネスの芽の探索・育成に取り組んでいます。
インキュベーションセンターの責任者である所長高橋隼人と、新規事業探策グループの川島淳が、どのような思いで活動をしているのか語ります。
未来検討タスクフォースから誕生した新規事業創出に特化した組織
髙橋 新規事業創出をミッションに、インキュベーションセンターが発足したのは、2023年1月のこと。きっかけは、前年の全社プロジェクト「未来検討タスクフォース」で、「近年、当社では新規事業があまり育っていない」という危機感が共有されたことです。当時は、営業や技術の関係者が月1回集まって新規テーマを議論していましたが、それぞれが本来の業務と兼務する体制には限界があり、専任の部署が必要という結論に至りました。私を含め3名が初期メンバーとして立ち上げを担い、「新しい事業を真剣に、スピーディーに創出する」ことを目的に、社長直轄の組織としてスタートを切りました。
ビジネスが具現化していく土壌づくりから開始
髙橋 当初はすべてが手探りで、先進企業へのヒアリングや新規事業をテーマにした外部セミナーへの参加を重ねました。見えてきたのは、斬新な事業アイデアを集めることに先立って、まずはそれを支える企業風土や人材といった土台づくりが欠かせないということです。そこで、有識者を招いた講演会や変革を担う人材育成プログラムの企画・開催に力を注いできました。
人と情報が集まる場づくりのため、本社オフィスのフリースペースを無償開放したのも新たな試みでした。スタートアップや地方自治体、NGOなどを招き、サイエンスやイノベーションをテーマにしたさまざまなイベントを開催し、これまで1万人以上にご参加いただきました。今年度からは「素材」に特化したグローバルなハブとして「Incubation CANVAS TOKYO」を本格運用する予定です。
また、これまで実施してきたビジネスアイディアコンテストを「IPPO」と改称し、再構築しました。従来は事業計画書の提出が必要など応募のハードルが高かったのですが、A4用紙1枚のアイデアから応募できるようにし、外部コンサルティング会社のメンタリングを受けながら、段階的に提案を磨き上げていくステージゲート方式としました。
徐々に育ちつつある新たな事業の芽
髙橋 設立から2年が経過し、組織としての厚みも増してきました。各事業部やR&D部門に埋もれていた有望なテーマを「人ごと」移管してきたことから、現在は約20名体制となりました。それぞれの多様な取り組みのなかで、一部で売上が立ち始めるなど、少しずつ成果が見られてきています。
これまで当社では事例の少なかったスタートアップ企業との協業も動き出しました。各種マッチングイベントへの参加を重ねることで接点が生まれ、すでに複数のテーマで共同契約が成立するなど、新たな共創の形が具体化しています。
「IPPO」では、2024年度にグランプリ受賞した「省エネ推進ソリューション」が事業化間近のフェーズに。提案者の川島さんには当センターに異動してもらい、現在100%コミットしてこのプロジェクトを推進しています。現在、お客様との有償実証実験も始まっており、当センターで育ててきた芽が実を結ぶ兆しを見せてきました。
- 風土醸成や人材育成
社外有識者を招聘した講演会を継続実施、社内提案制度の運営、社外の人を交えた変革人材育成プログラムの開催など - 仕組みやノウハウづくり
“千三つ”の新規事業を結実に導くためのステージゲート方式を採用 - 環境づくり
世界中から人と情報が集まる場「Incubation CANVAS TOKYO」の運用 - オープンイノベーション推進
今まであまり活動事例がないスタートアップ企業との協業を少しずつスタート - 事業化推進
事業会社やR&D本部にある未事業化テーマの切り離しと事業化の推進
グランプリ受賞を機に永年取り組んできたテーマを事業化へ
川島 以前、工場建屋・設備の施策で「省エネ大賞」をいただいた経緯から、当時所属していた事業会社の社長に直接声をかけてもらい、昨年のコンテストに応募しました。省エネは長く自分の使命の一つと考えていて、いずれ事業化したいという思いはありましたが、こんなにも早く実現に動き出せるとは思っておらず、グランプリ受賞は大きな転機となりました。周囲からの強い後押しもあり、感謝とともに、その期待に応えたいという気持ちがあります。
現在取り組むのは、設備の運用方法に着目し、エネルギー消費を大きく削減するソリューションです。私は中途入社で当社が4社目となるのですが、オフィスビルや商業施設の施設管理に携わるなかで、最新設備を導入しても省エネ効果を出せるのはその後の運用次第であることを実感してきました。現場の点検などで得られた情報が、社内でうまく共有されていないという課題も多く見ており、今回の取り組みはそこに一石を投じるものとなりました。
風土醸成・人材育成という使命
髙橋 インキュベーションセンターは、新規事業の創出と同時に、グループ全体に挑戦する風土を根付かせていくことも、重要な使命だと考えています。すべての原点となるのは「個人」のマインドセットであり、どれだけ優れた仕組みや画期的なテーマがあったとしても、最初の一歩を踏み出す個人の意思なしに、物事は前に進みません。
「IPPO」や「Incubation CANVAS TOKYO」などの取り組みを通し、社内の雰囲気が徐々に変わってきていることには手応えを感じています。日々の業務の傍ら「本当はもっとこういうこともやってみたい」と心のどこかで思っていた社員たちが、少しずつ行動に移し始めています。そうした思いを実現できる環境が社内にあることは、エンゲージメント向上のためにも重要です。
感性に響く価値の創出に向けて
川島 まずは現在の「省エネ推進ソリューション」の早期事業化に全力を注ぎます。すでに複数のお客様から引き合いをいただいており、事業の実現を通じて社会全体のエネルギー消費量の削減に少しでも貢献したいです。また、その先には今回の経験を活かして別の新たな事業に挑戦したいという思いもあります。省エネをキーワードに組織の連携を深めてきたのが今回のプロジェクトであり、同じことがほかの事業領域でもできるはずです。異業種からの中途入社である自分が新規事業を立ち上げることは、後に続く人に可能性を示す点でも意義が大きいと思っています。
髙橋 既存事業をしっかりと伸ばしながら、将来に向けた新たな事業の芽を育てていく。その「両利きの経営」の難しさは日々実感するところです。新規事業は長期的な視点で取り組んでいく必要があり、既存事業のようにすぐに収益に直結しませんが、成果が生まれない環境では「自分もやってみよう」という社員のマインドは育ちません。私たちは、新規事業を生み出す風土・仕組みづくりを継続しながら、川島さんのような成功事例を少しでも増やしていくことが重要と思っています。インキュベーションセンターの活動が、「心豊かな未来」に向けて挑戦する文化をつくり、事業ポートフォリオの大きな変革につながっていくことを目指したいです。
Incubation CANVAS TOKYOのウェブサイトはこちら
